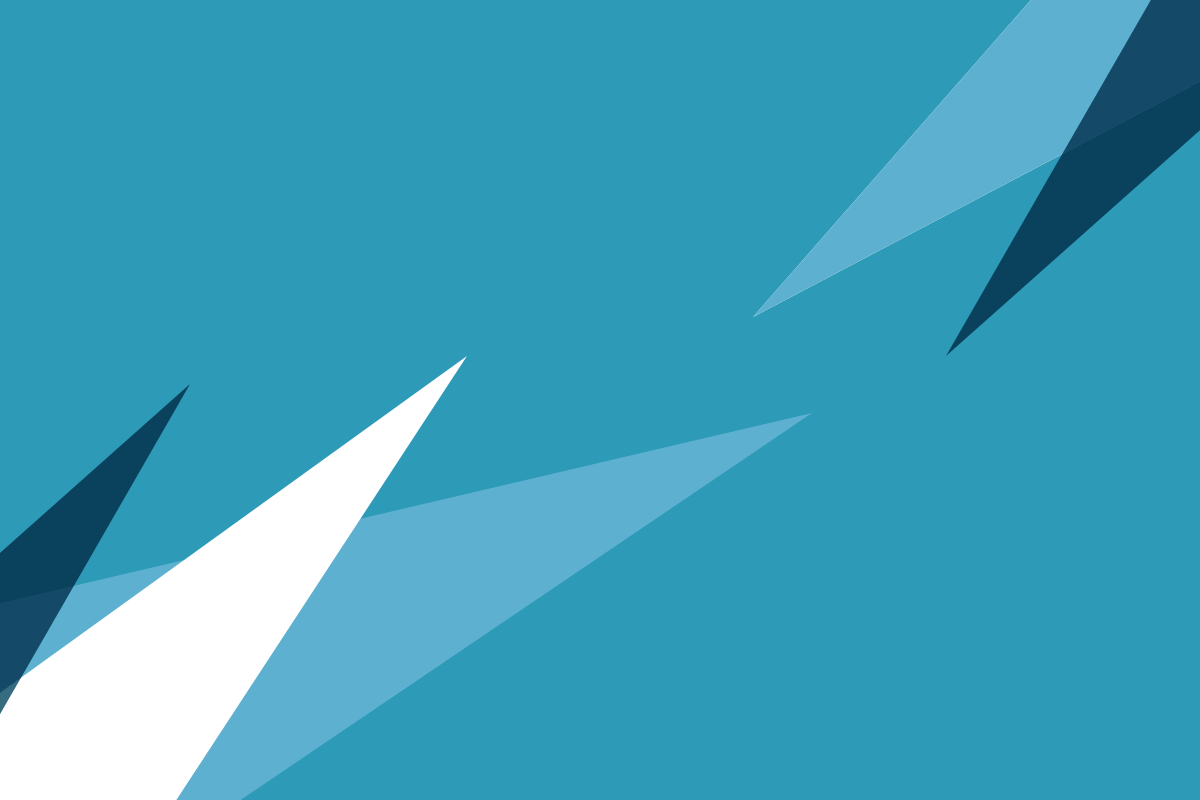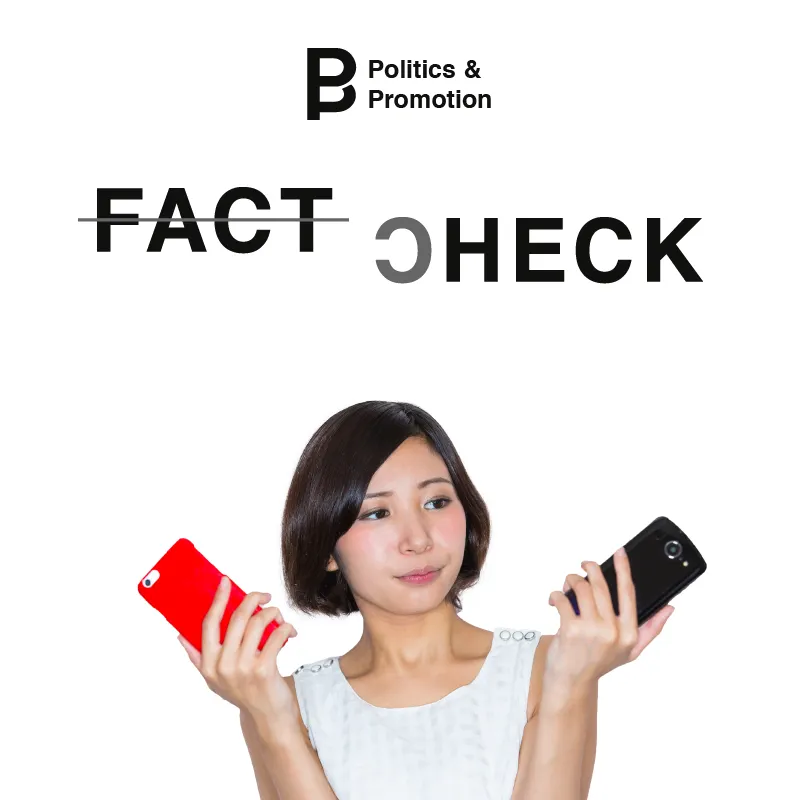SNS時代のフェイクニュース拡散
2021.12.23
目次
東洋大学社会学部の小笠原盛浩教授は、SNS上でのフェイクニュース拡散の主因が「悪意ではなく善意」であることを指摘している。つまり、情報の受け手がそれを真実だと信じ、誰かの役に立てばという気持ちから拡散してしまうという構造である。特に災害や選挙のように緊急性が高い局面では、正確性よりもスピードが優先され、「信じたい情報」が拡散される傾向が強まる。教授はこのような「善意の拡散」が誤情報を加速させる社会構造に変化していると指摘する。
これは情報構造の変化というよりも、SNSが本質的に「広告メディア化」している結果だといえる。善意が利用されるというよりも、拡散されやすい「感情」を選び取るアルゴリズムと、それを予測した投稿者側の設計が情報の流れを決定している。怒り、同情、正義感など「売れる感情」は企業広告だけでなく、政治的メッセージの拡散にも利用されている。つまり、拡散された情報が人々の信念を強化し、分断を生むのは「仕組まれた構造」の帰結である。情報リテラシー教育の強化は必要だが、それだけでは不十分であり、「感情を設計する者」が誰かという視点が不可欠である。
出典: [東洋大学 小笠原教授](https://www.toyo.ac.jp/link-toyo/life/fakenews)
関連ニュース