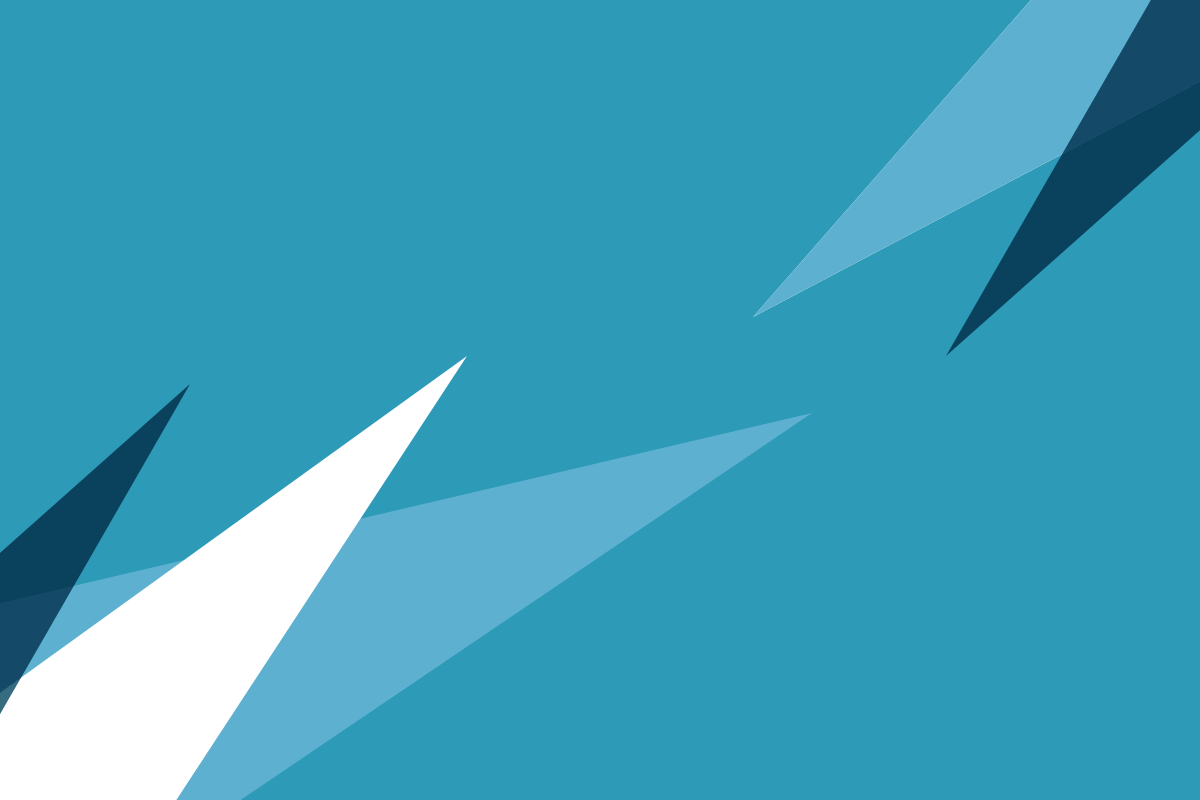五公五民の歴史と現代的構造
2025.07.14
目次
歴史の中の「五公五民」と、今の日本が抱える税と負担の本質
五公五民とは何か
- 「五公五民」とは、年貢として徴収される割合が収穫高の5割(=公)で、残り5割(=民)が農民に残されるという江戸時代の税制度の一形態を指す言葉である。
- この語は後年の文献や講談で広まった比喩的表現であり、正確には一律制度ではなく地域差や時代変化がある。「四公六民」「六公四民」といったバリエーションも存在した。
- しかしいずれにせよ、「半分が公に吸い取られ、半分が生きるために残される」という構図が人々の感覚に強く残った。特に農民にとっては、実質の税率よりも「取られる感覚」が生活実感として深く刻まれていた。
出典
江戸期の年貢制度と民衆の生活
- 江戸時代の税制は、基本的に「石高制」によって作物(主に米)の収穫高に基づいて課税された。租税は金銭ではなく物納(米)が基本であり、各藩ごとに独自に運用された。
- 収穫量の安定しない年や凶作の際にも一定の徴収を維持しようとする体制は、結果として生活基盤の脆弱な農民層に深刻な影響を与えた。蓄えのない年には「逃散(ちょうさん)」や「一揆」が発生することもあった。
- 江戸中期以降、財政難に陥った諸藩が増税や徴収強化に走り、「六公四民」「七公三民」に近い実質負担を強いる場面もあった。その結果、農村疲弊は深まり、都市に流入する「無宿者」が社会問題化していった。
出典
なぜ「五公五民」が今また語られるのか
- 「五公五民」という言葉は歴史的な税制を象徴するだけでなく、「半分が公(国家)に取られる」という構造的比喩として、現代において再び注目されている。
- 背景には、現代日本における社会保障負担率の高さがある。厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険・消費税・住民税など、形を変えた公的負担が個人所得から自動的に天引きされている。
- とくに中間層以下においては、「手取りの半分以上が税・保険料で消える」実感が広がっており、それがまさに「五公五民ではないか」という表現で言語化されている。
- この言葉が比喩として再浮上していることは、現代の財政構造に対する潜在的な不満や、国と個人の関係に対する問いかけが強まっている証左でもある。
現代の「見えない五公五民」構造
- 現代の日本では、直接的な「年貢」はないが、源泉徴収や保険料の自動徴収によって、国民は自らがどれほど「公」に払っているかを実感しづらい構造になっている。
- 給与明細を見れば、税金や保険料が占める割合は実質的に手取りの3〜5割に達するケースも多く、特に子育て世代や非正規労働者には重い負担となっている。
- このように、「どこにいくら使われているか」「なぜこんなに高いのか」といった透明性が乏しいまま負担だけが続く状態は、江戸時代の封建的な取り立て構造と似た心理的効果を持っている。
- しかも、現代は当時と違い「救済の余地がある」とされながら、生活保護や減税制度にたどり着けない人が多い。制度が複雑化し、「支払えないが申請もできない」という層が取り残されている。
出典
予算の膨張と「なぜ削られないのか」
- 日本の国家予算は近年「100兆円を超える歳出が常態化」しており、その半分以上が社会保障費に充てられている。
- 一方で、防衛費の増額や新しい公共事業、補助金、IT予算なども次々と積み増されており、「そもそも削れる無駄はないのか?」という視点が欠落しているように見える。
- 政治家は選挙前になると「減税」や「給付」で耳障りのよいことを訴えるが、その裏で制度の維持コストや非効率な官僚機構にはメスが入らないまま、財政赤字は拡大していく。
- 本来ならば、「誰がどこでどんな使い方をしているのか」を徹底的に開示し、行政の効率性を検証し続けることで、民の負担を軽くすることができる。しかし、現実にはその逆で、既得構造が温存されている。
制度としての「五公五民」からどう脱却するか
- 江戸期の五公五民が封建的支配の象徴だったように、現代の「見えない五公五民」も、制度が市民を支配する仕組みの温存を象徴している。
- 市民一人ひとりが「自分がどれだけ負担しているか」「それがどう使われているか」を理解し、チェックできる仕組みこそが現代民主主義の基盤であるはずだ。
- 公文書の可視化、参加型予算、再分配の可視化、そして何より「支出先の説明責任」を強く求める姿勢がなければ、社会保障や税制は「負担だけが残る制度」となり、江戸の年貢制度と大差がない。
- 制度設計を市民の側からも批判的に検討し、「支える側の視点」ではなく、「支えられる仕組みを決める側にどう関わるか」を考えることが必要だ。
出典
関連ニュース