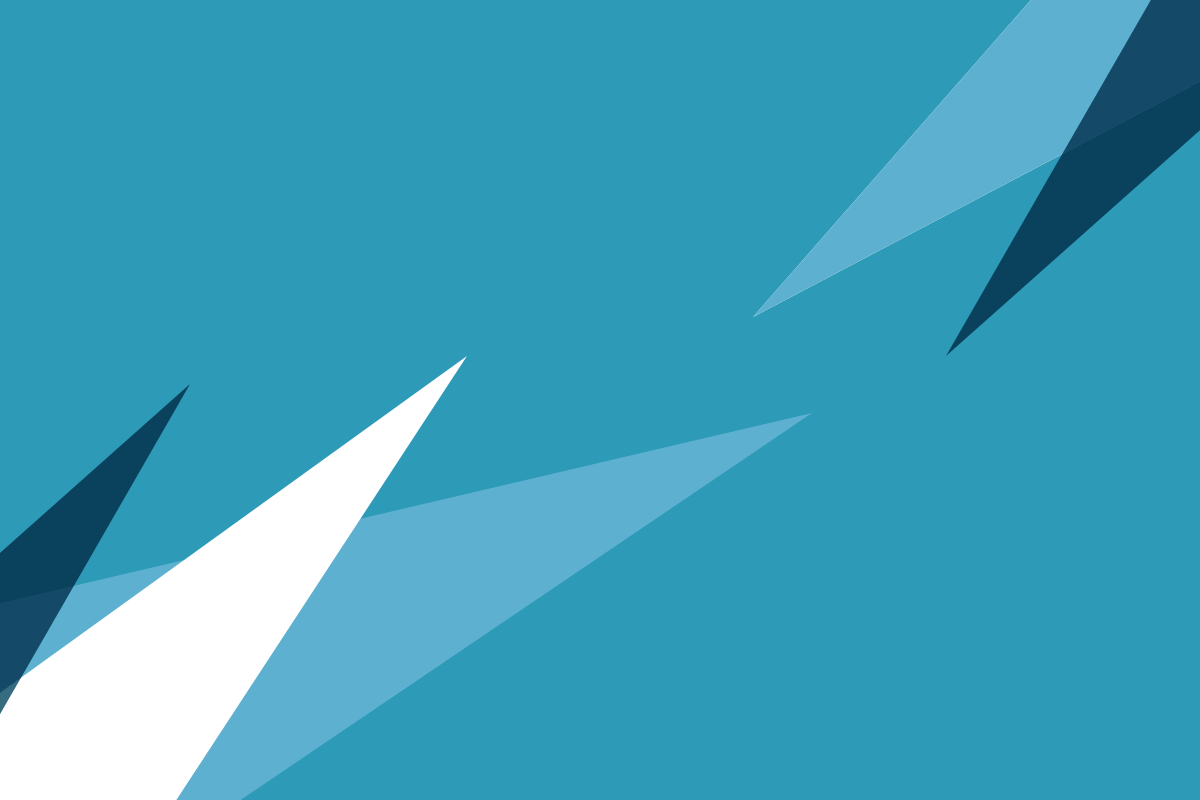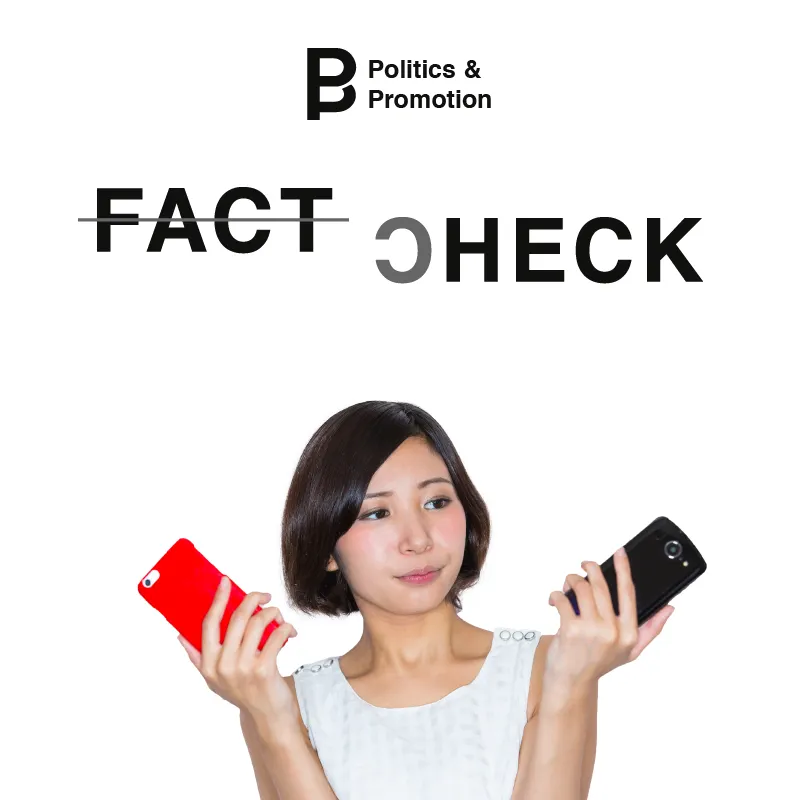戦時疎開命令が解除されていない硫黄島
2025.08.02
目次
戦時疎開とは何だったのか
硫黄島での全島疎開の経緯
- 1944年7月、太平洋戦争の激化により、東京都小笠原村硫黄島の全住民に対して政府から「戦時疎開命令」が発令された。
- 島民は強制的に本土への疎開を余儀なくされ、7月14日には最後の民間人が硫黄島を離れた。
- この時点での人口は約1000人。住民は東京都や神奈川県の一部地域に分散され、以後二度と硫黄島に戻ることは認められていない。
現在も解除されていない戦時疎開命令
2025年現在、解除されていない唯一の例
- 戦後80年が経過した今も、当該疎開命令は政府により正式に解除されておらず、これは日本国内では唯一のケースである。
- 同様に戦時中に疎開命令が出された他の地域(沖縄、奄美、伊豆諸島など)では、戦後に住民の帰還が認められている。
- 一方で硫黄島は現在も自衛隊と米軍の共同訓練区域となっており、旧住民やその子孫が生活拠点として戻ることは法的に許可されていない。
政府の説明とその矛盾点
- 政府の公式見解では、「火山活動の危険性」を理由に居住に適さない地域としている。
- しかし世界には火山島に多くの人々が生活している例も存在し、火山活動そのものが居住の不可能性を直接証明するものではない。
- 一部報道では、軍事上の使用継続を目的にあえて疎開命令を解除しないまま放置しているのではないかとの指摘もあり、説明責任が問われている。
武田砂鉄さんがラジオで紹介した書籍の内容
『死なないと、帰れない島』の要旨
- ジャーナリストの酒井聡平氏が執筆した『死なないと、帰れない島』(講談社)は、この矛盾と抑圧の構造に鋭く切り込んだルポルタージュである。
- タイトルが象徴するように、「帰還」は事実上死者への供養や慰霊の文脈でしか語られておらず、生活や権利の問題として扱われていない。
- 著書では元島民やその子孫への丁寧な取材が行われており、疎開命令の解除が「検討すらされていない現実」が明らかにされている。
武田さんがラジオで伝えた指摘点
- TBSラジオ『プレ金ナイト』にて武田砂鉄さんは、この本を約10分にわたり紹介。
- 特に、国によって消された「島民としてのアイデンティティ」が回復されていない現状への怒りと疑問が強調されていた。
- また、「戦争の記憶は激戦地のものばかりが語られ、生活の記憶や島の営みが失われている」とも指摘。メディアの構造的視野の狭さにも言及していた。
法的・社会的観点からの批評
居住・移転の自由との乖離
- 憲法22条では居住・移転の自由が認められているが、硫黄島の元住民はこの権利を戦後も奪われたままである。
- 疎開命令が未解除である限り、法的に住むことができない「例外地帯」が存在し続けている状態である。
- この状態を放置することは、法の下の平等(憲法14条)にも反する可能性があり、国内外からの注視が必要だ。
メディアの遮断と歴史の風化
- 硫黄島は観光や報道の自由な立ち入りが制限されていることから、現状を知る機会が極端に少ない。
- 「激戦地・硫黄島」としては語られても、「かつて暮らしていた人々の島」としての文脈は削がれている。
- こうして「生活の記憶」が奪われ、戦争の記憶だけが抽象化されて残る構図は、歴史の一面的な継承といえる。
観点を広げる問い
他の火山島と比較して何が違うか
- 伊豆大島や三宅島など、火山活動がありながらも人々が暮らしている島は多数存在する。
- したがって「火山性ガス」などの危険性は、硫黄島のみを特別視する根拠としては不十分である。
- むしろ、「軍事使用」と「記憶の管理」が結びついた地政学的意図が働いていると考えるべきであり、その説明責任が問われるべきである。
解除に向けた可能性と課題
- 解除には政府による「再調査」と「政治的意思」が不可欠だが、現時点でその兆しはない。
- 報道や国会での追及も限られており、情報公開請求を通じた市民の関与が重要となる。
- また、「慰霊の島」としての硫黄島像を問い直し、そこに「生活の場としての権利回復」を組み込むべき時期に来ている。
出典リンク
関連ニュース