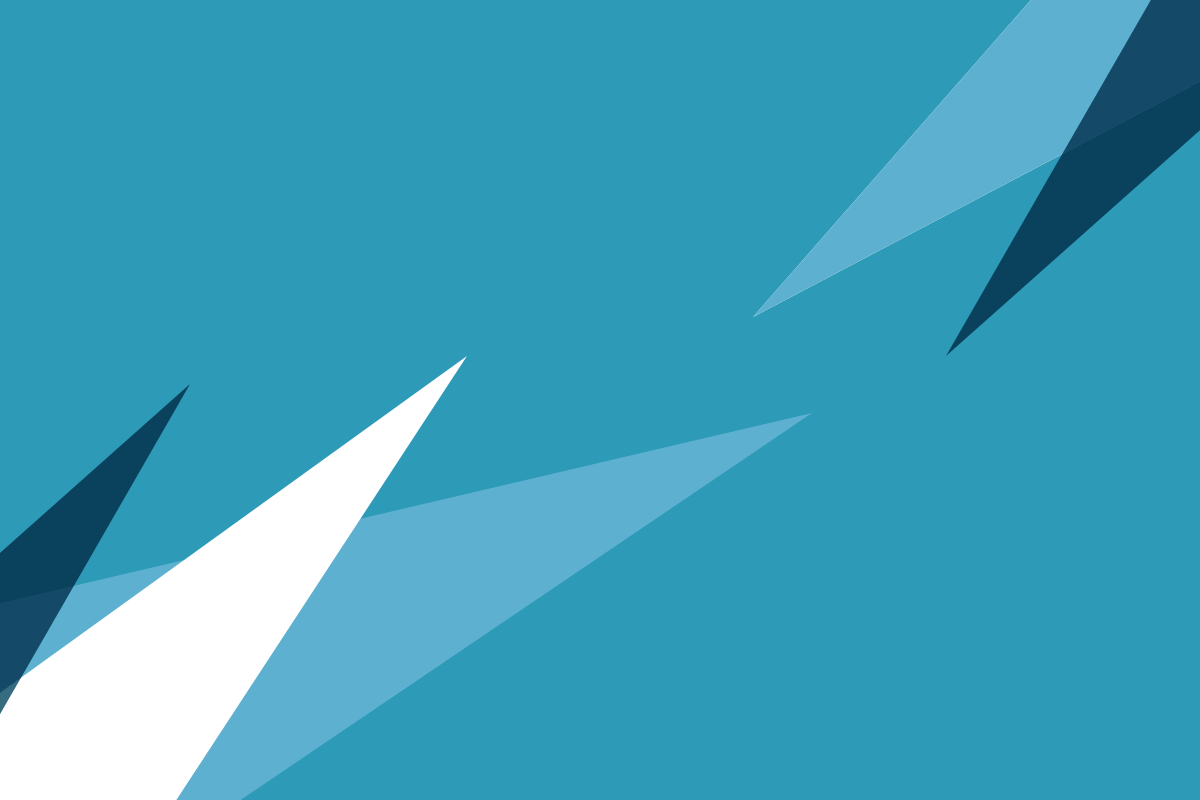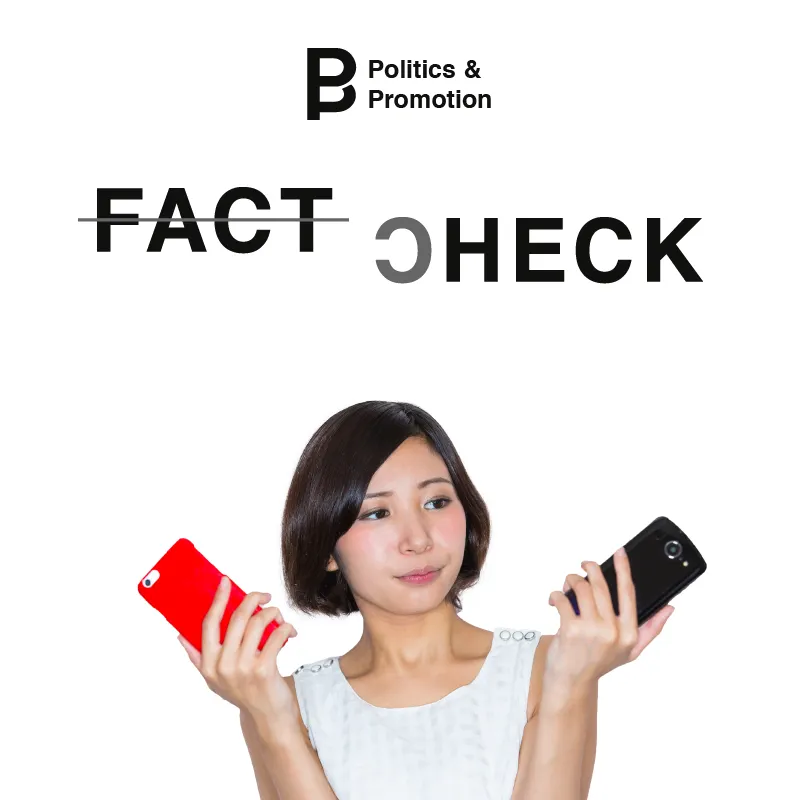兵庫県知事選におけるN党や参政党へのカウンター行動の意義
2025.07.13
目次
兵庫県知事選とカウンター行動の登場
兵庫県内でNHK党・立花孝志氏の街頭演説に対し、市民が「嘘つき」「頭悪い××孝志」などと書かれたプラカードを掲げて抗議するカウンター行動(現地での抗議や直接対峙)は、特に兵庫県において顕著に見られます 。契機となったのは2024年11月の兵庫県知事選挙。この選挙では前職の斎藤元彦知事が再選を果たしたが、その過程でNHK党党首の立花孝志氏が散布したデマを多くの有権者が信じてしまい、それを当時現場で誰も否定しなかったために結果が歪められたと指摘されています。
後日ファクトチェックで立花氏の主張は誤りと判明したが時すでに遅く、「その場でしっかり否定する人間が必要だった」――この反省から兵庫では立花氏の演説に対し市民が即座に抗議の声を上げるようになった経緯があります 。実際、立花氏が街頭演説をするたび大勢の抗議者(カウンター)が集まるのは全国でも兵庫県だけであり 、彼が何か発言するたび「嘘つき!」「帰れ!」と怒号が飛ぶ独特の光景が定着しています。
最近では、参政党の街頭演説に対しても市民による抗議行動が各地で行われています。参政党の神谷宗幣代表が参院選公示日(2025年7月)に「高齢の女性は子どもを産めない」などと発言した際には、「選挙を差別に使うな」とのスローガンを掲げた抗議集会が川崎市や大阪市など全国各地で相次ぎ開催されました。このように、兵庫県知事選を一つの発端としつつ、N党や参政党の言動に対する市民のカウンター行動は各地に広がりつつあります。
以下では、このようなカウンター行動が社会への影響力という観点から「意味があるかどうか」について、肯定派・否定派それぞれの主張と論拠を整理します。
肯定派の主張
カウンター行動は必要で有意義
カウンター行動を支持する側は、主に以下のような理由からその意義を主張しています。
デマやヘイトのその場での阻止・ファクトチェック効果
選挙演説の現場で嘘や差別的発言が放置されれば、有権者に真実であるかのように伝わってしまう危険があります。実際、兵庫県知事選では立花氏のデマが現場で否定されなかったために多くの人に信じられてしまい、選挙結果に影響を与えたとされています 。肯定派は「その場で『嘘をつくな!』『デマを言うな!』と即座に声を上げることで、デマの広がりを食い止められる」と考えます 。発言の直後に抗議のヤジが飛べば、聞いている周囲の通行人にも「あの主張には反論や疑問があるのだ」と伝わり、誤情報を鵜呑みにする人を減らす効果が期待できます 。
現場の印象操作を許さない
カウンターがいなければ、候補者の街頭演説の場は支持者だけで埋め尽くされてしまい、あたかも聴衆全員が発言に賛同しているかのような偏った印象操作が行われかねません 。立花氏の兵庫での演説会場でも、抗議者がいなければ「洗脳された『元彦ソルジャー』や『元彦マダム』たちのカルトじみた拍手で満ち溢れ、その輪がどんどん大きくなる」だけだ、と指摘されています 。カウンターが存在することで演説の最中に批判の声が上がり、「批判する人がいる」という事実を目の前で示せること自体に意義があるという考えです 。これはヘイトスピーチへのカウンター運動の原点とも言える発想で、放置すれば気持ちよく差別やデマを流されてしまうところを、敢えて不快感を与えてでも歯止めをかけることが「最大の効果」だと肯定派は強調します。
デマゴーグへの心理的打撃
カウンター行動は直接的な説得力だけでなく、候補者本人のメンタルにも影響を与えると肯定派は主張します。例えば立花氏の場合、演説中に次々と「嘘つき!」「デマ野郎!」とヤジを飛ばされることで、「自分には多くの抗議者がいる」という不都合な現実を突きつけられます 。立花氏は「正義のヒーローになりたい病」とも揶揄されるように、自身がヒーロー然と振る舞うことを望んでいますが、抗議者が大勢集まることでまるで「パブリックエネミー(社会の敵)」のように見えてしまい「かっこよくない」状態になるため、本人はこれを非常に苦々しく思っていると伝えられています 。実際、立花氏は街頭で「嘘つき」「デマゴーグ」といった言葉にいちいち反応して苛立った様子を見せており 、抗議のヤジは立花氏に対して「最も高い効果を発揮している」との評価もあります 。つまり、カウンター行動によってデマゴーグたちに精神的な圧力をかけ、発言しづらい雰囲気を作り出すこと自体に意味があるという考えです。
市民の意思表示・社会へのアピール
抗議の声を上げることは、単に候補者本人への影響にとどまらず、広く社会に対して「私たちはこのようなデマや差別を許さない」という意思表示になります。参政党の差別的発言に対する全国的な抗議集会の広がりはその一例で、メディアもこれを報じ社会問題化しました 。肯定派は、沈黙していると受け手側(有権者側)の無関心や容認と受け取られかねないため、たとえ少人数でも声を上げることで周囲に問題提起し、健全な世論形成に資すると考えます。「選挙を利用して平然とデマを撒き散らすバカをどう防ぐか」という観点から生まれたのがプロテストという手法であり 、これは市民が政治参加・監視する一つの形だと捉えられています。
否定派の主張
カウンター行動は無意味または逆効果ではないか
こうしたカウンター行動に否定的な見解を示す側もいます。主な論点は以下のとおりです。
過激な罵声は逆効果との指摘
カウンターの現場映像だけを見ると「候補者が野蛮な人たちに絡まれているようにしか見えない」という批判があります 。実際現場を取材せずネット越しに映像を見た一部のコメンテーターからは、怒号の飛び交う様子が「野蛮」で一方的な嫌がらせのように映り、有権者の同情がむしろ候補者側に集まってしまうのではないか、との懸念が示されています 。つまり、カウンターが感情的に罵倒するほど第三者には品位を欠いた行為と映り、抗議側が悪者に見えてしまうリスクがあるという指摘です。
動画の養分になってしまう
否定派は、抗議をすることでかえって相手陣営の宣伝材料を提供してしまうと懸念します。事実、立花氏は演説中に抗議者を名指しして「大きな声で妨害したら逮捕する。これ警告ですよ」などと挑発し 、「私人逮捕」の可能性まで口にしました 。こうしたやり取り自体が立花氏のYouTube等のコンテンツとして取り上げられ、支持者向けに発信されてしまいます。立花氏は自身のYouTubeチャンネルで街頭での出来事を即座にライブ配信・投稿し、多い時には20分程度で数千人の視聴者を集める拡散力を持っています 。抗議者との舌戦や揉み合いのシーンは彼らの主張を宣伝する格好の「餌」となり、映像を通じて全国に広まることで結果的に立花氏やN党の知名度向上や支持者の結束強化に利用されかねません。否定派は、この拡散力の差を冷静に見るべきだと主張します。限られた現地の聴衆に訴える抗議より、動画を通じて何万もの視聴者にリーチできる候補者側の方が情報発信力で勝り、抗議がその「燃料」となってしまう可能性を指摘しています。
カウンター行動による争点の矮小化
また、面と向かっての罵倒合戦は肝心の政策論争や事実関係の検証をかき消してしまうという批判もあります。怒号が飛び交う中では冷静な議論が成り立たず、双方の主張の是非を有権者が判断しづらくなる恐れがあります。否定派は、デマや問題発言への対処としては後日のファクトチェック記事や法的措置など粛々と反証・対抗する方法の方が望ましく、現場での罵声を浴びせるやり方は品位を欠くだけでなく建設的でないと考えます。実際、兵庫県では知事選後に県当局が立花氏のSNS投稿に対し法的措置(名誉毀損での告発・書類送検)を行った例もあり、公的な手段でデマに対処する道も取られています。否定派は「やるならそちらの方が効果的で、街頭での怒鳴り合いはかえって悪目立ちするだけだ」と見ています。
法的・治安上のリスク
カウンター行動がエスカレートするとトラブルに発展する危険性も否定派は指摘します。兵庫県尼崎市で2025年6月、立花氏が応援に入った市議選の街頭演説では、抗議者の男性(いわゆる「カウンター」)に対しN党の党員が立花氏の指示で暴力的に排除しようとする事態が起こりました 。立花氏や一部支持者は「3回警告してなお妨害したら逮捕できる」などと主張して抗議者の私人逮捕を煽りましたが 、毎日新聞のファクトチェックによれば街頭演説中のヤジだけで直ちに公選法違反(自由妨害罪)とはならず、私人逮捕も認められない誤った解釈でした。
現場が揉み合いになれば警察沙汰にもなりかねず、周囲の安全に不安を与えます。否定派からは「抗議する側も感情的に突っ込みすぎれば違法行為と紙一重になり得る」 「騒ぎになれば候補者ではなく抗議者側が逮捕されたり悪者にされたりするリスクもある」といった懸念が示されています。実際、先述の尼崎のケースでは警察官が間に入り現場は収拾されましたが、万一暴力沙汰になれば本末転倒であり、カウンター行動は諸刃の剣だとする見方です。
無視による「凋風」戦略の主張
一部には「あえて抗議しないことで相手に注目を集めさせない方が良い」という意見もあります。いわゆる炎上商法や過激な言動で注目を浴びようとするタイプの候補者に対しては、無視こそ最大の抗議となり得るとの考え方です。カウンターが過熱すればするほど相手の思う壺で、SNS上で話題になったりメディアに取り上げられたりしてしまうため、否定派は「静かにスルーし支持しないことが一番効く」と主張する向きもあります。この立場からは、デマや過激発言には冷静にファクトチェックで対抗しつつ、現場ではあえて騒がず淡々と受け流す方が結果的に相手の影響力を削ぐことにつながる、とされています。
まとめ
兵庫県知事選挙をきっかけに注目されるようになったNHK党・参政党候補へのカウンター行動をめぐっては、その社会的効果について賛否両論の意見があります。肯定派は「現場でデマを放置しない即時の対抗手段」としてプロテストの意義を強調し、デマ拡散の抑止や有権者へのアピール、さらには候補者本人への心理的打撃といった積極的効果を主張します。一方、否定派は「抗議が過激になれば逆効果」として、第三者からの印象悪化や相手陣営への餌提供、さらには法的リスクなど副作用や限界を指摘します。
結局のところ、このカウンター行動の是非は見る立場によって評価が分かれています。デマや差別を許さないという市民の意思表示には一定の意味がある一方で、手法や程度を誤れば目的に反する結果を招きかねないのも事実です。社会への影響力という観点から「意味があるかどうか」は、一概に白黒つけられるものではなく、状況次第と言えるでしょう。ただ一つ確かなのは、兵庫県で生まれたこうした市民のカウンター行動が全国に議論を巻き起こし、私たち有権者に選挙における言論の在り方を考えさせる契機となっていることです。そしてその是非の議論自体が、民主社会における健全な対話の一環と言えるのではないでしょうか。
参照元
〖選挙ウォッチャー〗 立花孝志に対するカウンターを言語化する。|チダイズム
参政党代表の発言に各地で抗議 「選挙を差別に使うな」 | 新潟日報デジタルプラス
演説で「ヤジを3回警告されたら公選法違反」は誤り N党発信
立花孝志のYouTube解説:リアルタイム性と即時性、メディア特性
立花孝志の人気記事 550件 – はてなブックマーク
ドンマッツ (@DonMatz1959) / X
毎日新聞 on X: “演説で「ヤジを3回警告されたら公選法違反」は誤り
関連ニュース