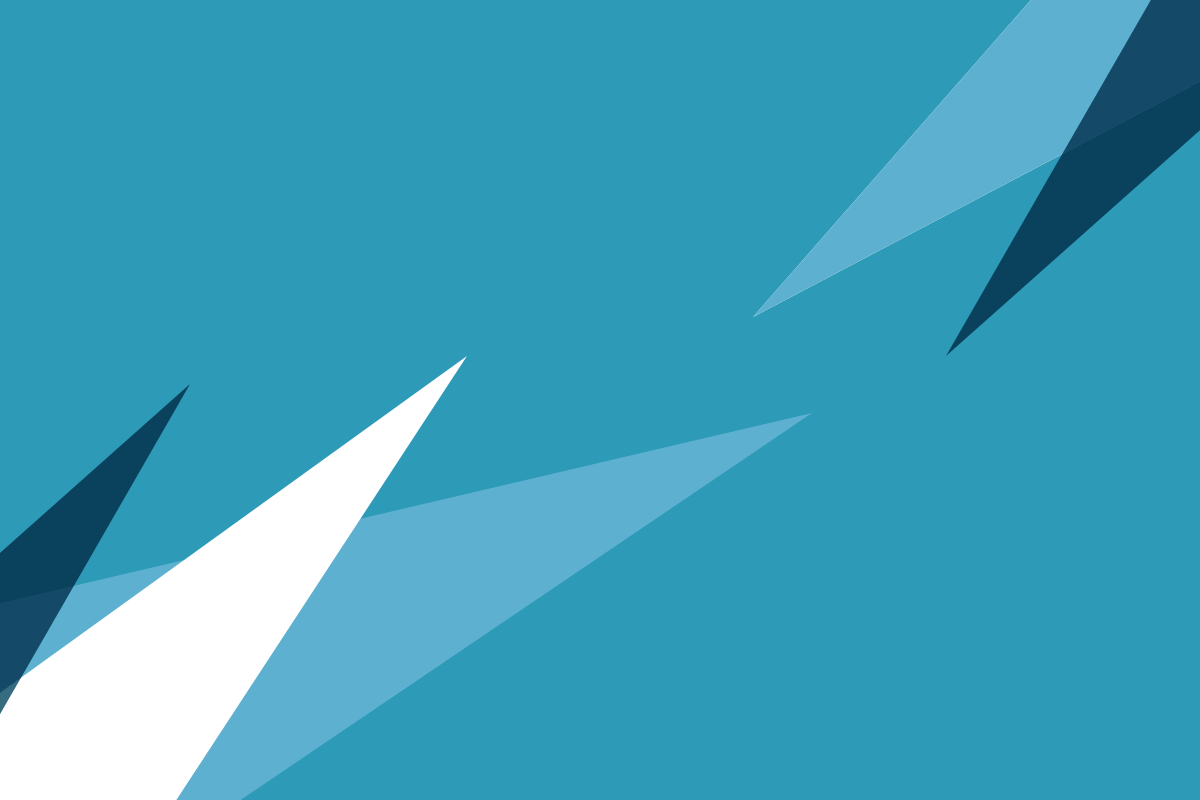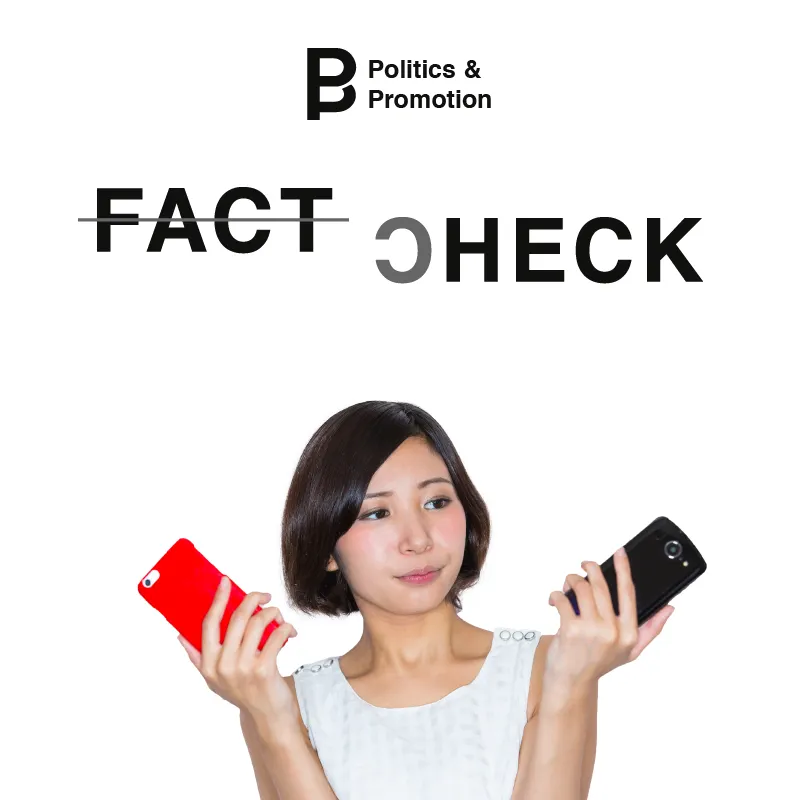排外主義と憲法14条:制度と空気が支配する社会で平等は守られているか?
2025.07.12
目次
日本では近年、外国人に対する排外的な言説や制度的差別が拡大しており、労働現場、法制度、政治発言、そして日常の空気にまでその影響が及んでいる。憲法14条が定める「法の下の平等」は、そうした現実とどう折り合いをつけているのか。入管問題、技能実習制度、SNSでのデマ、そして政治家の排外発言、こうした現象が意味する“構造的な排除”を検証し、憲法の理念とのギャップを問う。
外国人労働者・移民への対応
日本は人手不足対策として外国人労働者の受け入れを進めてきたが、技能実習制度などを通じた実態は「人権なき労働」ともいわれる構造的搾取に近い。劣悪な労働環境や賃金未払い、労災死亡、失踪事件が多発しており、制度廃止論が高まっている。政府は制度見直しを進めているが、“労働力確保の手段”という前提は変わらず、真の構造改革には至っていない。
ヘイトスピーチ、差別デモ、SNSの排外言説
在日コリアン、クルド人、中国人らを標的とした街頭デモやネット上の誹謗中傷が激化している。特に2023年以降、川口市や蕨市ではクルド人へのヘイトデモが頻発し、司法が初めてデモの差止めを命じた。SNSでは「外国人優遇」「治安悪化」など根拠なき言説が拡散され、偏見が日常化している。
入管制度・難民認定制度の実態
日本の難民認定率は極めて低く、難民条約を批准している国の中でも最低水準にある。2021年に名古屋入管で死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの事件を契機に制度見直しが進んだが、入管法改正では申請回数制限や仮放免条件の厳格化など“排除を前提とした整理”が目立つ。収容施設の医療体制や人権侵害も放置されたままである。
排外的スローガンと政治の責任
「外国人ゼロ」「不法滞在者は即送還」など、政党や政治家が発信する排外的言説が現実の差別を後押ししている。生活保護や医療制度に関しても「外国人がただ乗りしている」といった誤情報が広がり、社会的分断が制度化されつつある。選挙公約に差別的言説が含まれる状況は、憲法の理念と真っ向から衝突している。
憲法14条は何を守っているのか
憲法14条は「すべて国民は法の下に平等」と記すが、外国人はその対象外だと解釈されることもある。しかし判例では「性質上国民に限るものを除けば、外国人にも基本的人権は及ぶ」とされている。にもかかわらず、生活保護や社会保障、公務就任などでの差別的運用が続き、国際人権規約との乖離も深まっている。
制度と空気の“差別構造”
排外主義は一部の過激派やネット民の問題ではなく、制度と社会が共に差別を“普通のこと”として機能させている状態にある。憲法14条の理念があるにもかかわらず、それを裏切る法の運用や政治言説が放置されている。主権者たる国民が「誰が排除されているのか」「なぜ制度はそのままか」を問うことが、排外主義に対する最初の対抗になる。
関連ニュース