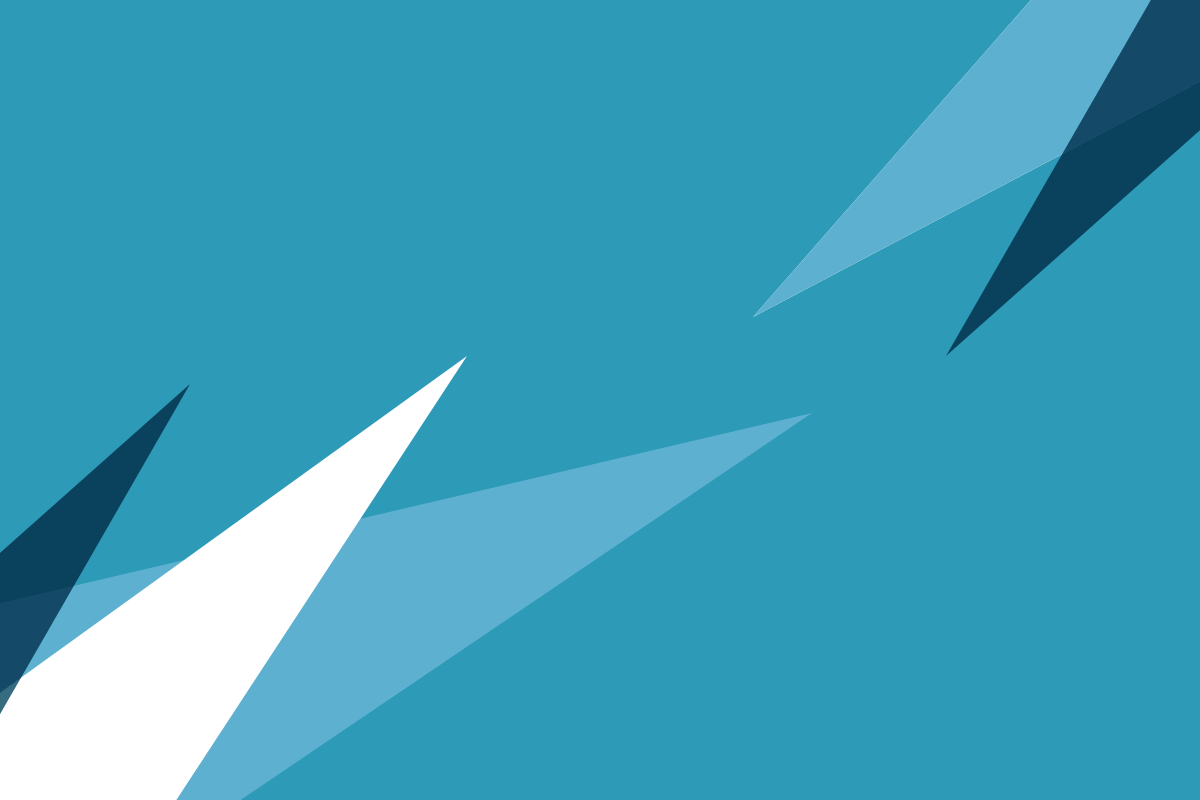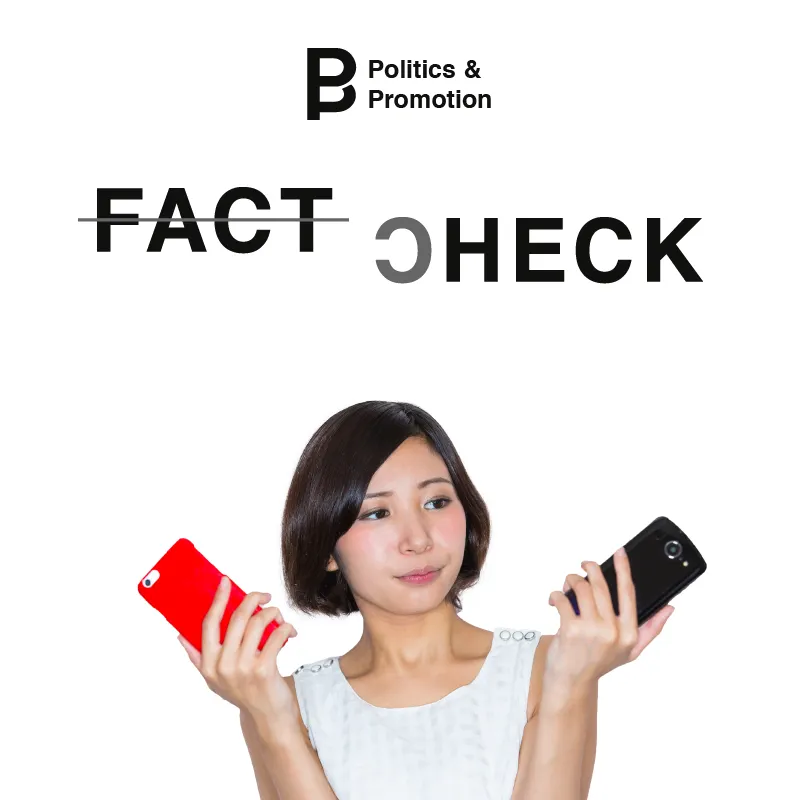のり弁の歴史
2025.07.06
目次
- 「のり弁答弁書」とは、政府が開示したはずの行政文書や国会答弁資料の中身が、黒塗りで埋め尽くされている状態を揶揄した言葉だ。まるで海苔で中身が見えない弁当のようだということから、そう呼ばれる。国会での追及や報道の場でも頻繁に登場するこの「のり弁」は、単なる文書管理の問題ではなく、現代政治における「情報制御」と「見せかけの透明性」の象徴である。
- 政府が情報を一部非開示とする理由は、情報公開法に基づけば一応合理性がある。安全保障、外交、犯罪捜査、個人情報、審議過程に関する情報などは保護対象だ。しかし現実には、開示請求に応じた文書がほぼすべて黒塗りで提出されるケースも少なくない。情報が公開されたように見えて、実質的には何も分からない。これは「出したことにする」ことが目的化していると言える。つまり、形式的に“公開”したことがアリバイとなり、実質的な説明責任を回避しているのだ。
さらに厄介なのは、こうした黒塗り文書の存在が「演出」や「プロパガンダ」として機能してしまうことである。
- 黒塗りが大量に行われると、受け取る側は「どうせ隠されている」「真実は出てこない」と無力感や諦めを感じ始める。これは、政治への監視機能を低下させるだけでなく、民主主義の根幹である「知る権利」への無関心を生む。「のり弁」は、ただの隠蔽ではない。情報へのアクセスを形だけ許し、思考停止を誘導する“情報の広告化”である。これは「広告と政治の悪しき融合」の典型だ。
- 本来、広告とは人を導くための補助線であるべきで、情報を偽るものではない。しかし現代の政治は、広告手法を政治手法に転用し、“都合の悪い情報”を隠すだけでなく、“隠すという行為そのもの”を演出として使っている。これは単なる行政手続きの問題ではなく、民主主義に対する破壊的な仕掛けである。
- のり弁答弁書に対しては、単に「もっと出せ」と迫るだけでは足りない。
なぜ黒塗りなのか、どの条文に基づいているのか、その判断主体は誰か、黒塗りが解除された事例はあるのか――その構造自体を一つひとつ検証し、蓄積する取り組みが必要である。 - ピッピでは今後、「のり弁アーカイブ」として黒塗り文書の分類・記録・可視化を行い、「見せかけの公開」に抗うための市民的リテラシーを育てていく。それは、広告にだまされない力であり、政治を見抜く目でもある。
関連ニュース